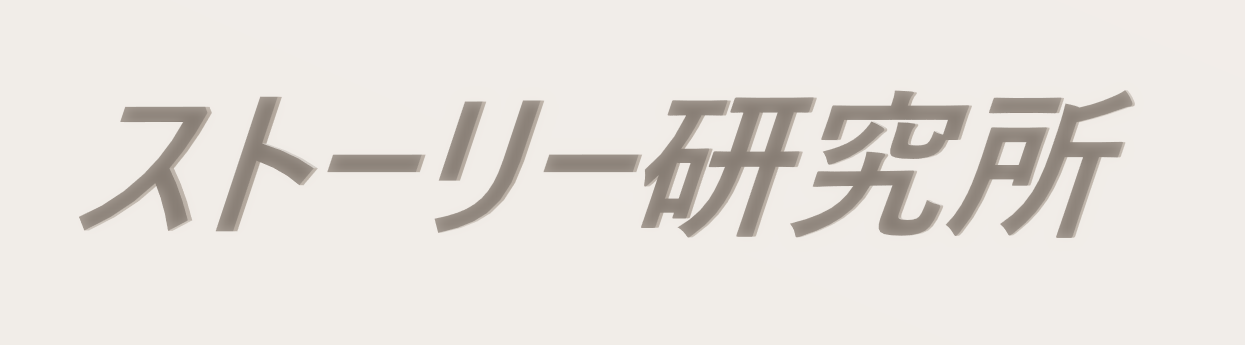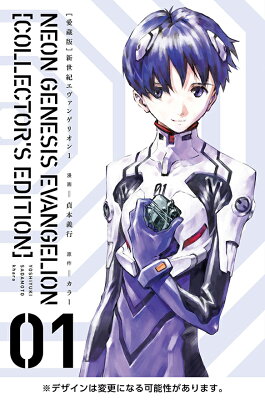Amazon Primevideo
 「全てのエヴァンゲリオンファンへ、おめでとう。」
「全てのエヴァンゲリオンファンへ、おめでとう。」って言われたら、ジーンと来る人にオススメ。
初見さんいらっしゃい! ではない。
新劇場版エヴァ、結局全シリーズ映画館で観なかったなー。
まだギリやっているところあるかなー。
Amazon Primevideoをポチる。
え?
公開?
もう?
はい、まさかのアマプラで観れるという……。
最近は映画からサブスクまでが早すぎますね。
結局、新劇場版シリーズは全てアマゾンで観てしまいました。
さて、ガチ考察勢とか名乗っておきながら、普段シナリオ考察しかしていなので、たまには考察っぽい事をしてみます。
資料や情報考察(整理)って、単に時間かかるだけの作業なので好きじゃないですが、本作シン・エヴァンゲリオンは比較的分かりやすくストーリーに出ていたので、書いておきます。
※全てネタバレありです。
エヴァンゲリオンとは何だったのか?
初めにこれだけ書かせて下さい。
エヴァンゲリオンという作品がやろうとした事は、新しい何か? です。
顕著に顕れたのは、
・作画とデザイン → 映像
・言葉で語らないドラマ → シナリオ
の二つで、シナリオについては映像のおまけについてきたものです。
エヴァンゲリオンは、アニメ界の革命児ではありましたが、特徴は、極端に尖った「画」。
漫画でも小説でも、極端に目立たないとブームにはならないですね。
特にエヴァが革命的だったのは、カメラアングルや構図。
街とロボット距離感を出す遠近法、ビル群を足元に並べる構図。
これらは、「特撮の作り方」です。特撮をアニメに落とし込んだ構図で表現していました。
時間表示のパネルを斜めから映すパース、艶めかしく中学生の体のラインを映すプラグスーツなどなど、センスも尖っています。
またガイナックスの「トップをねらえ」、「オネアミスの翼」などから脈々と続くSF要素。
「プリンセスメーカー」などのエロ要素。
培った全てを使い、限界まで尖った映像に命をかけた作品が、エヴァンゲリオンです。
斬新な映像のパレードで、だからこそ、シナリオも尖りました。
メインプロットをほぼ書かない。
圧倒的に魅力的な絵があったので、詳細のストーリーを省き、謎と少年少女の葛藤だけにスポットを当てています。
小説ではまず不可能な作り方です。
漫画でもたぶん無理です。
映画でたまにやっている作品はありますが、基本はできません。
だって、観ている人が理解できないから。
エヴァもそう。理解できません。説明されてないんだもの。
それでも売れたのは、尖り切った画と、そういうものを求める時勢があったからだと思います。
狙ってできた事では無いでしょうし、ここまでのビッグタイトルになるとは、誰も予想できなかったはずです。
兎に角、油の乗り切った「今が全盛期クリエイター」の狂人的なエゴ作品こそ、エヴァンゲリオンです。
エヴァを語る多くの人は「なんだか良く分からんけど、好き」でしょう。
作家達の狂気にあてられた名作が、テレビ版(と初めの映画二本)でした。
エヴァ新シリーズの目的
三つです。
一つは、前作のオチが伝わっていなかったので、今回は分かるように書く。
※これは、度々庵野さんがインタビューなどで語られています。
二つ目は、ファンサービス。
三つ目は、クリエイターサービス。
ビッグタイトルなので、各方面に影響があります。経済は勿論、アニメ業界の指針、また新しいクリエイター達の活躍の場にもなります。
特に本作、前作あたりは三つ目の意義が強いですね。
過度な見栄えが重視され、限界までアニメの可能性とエゴを追求していました。
ただ、本作はちゃんと説明する、が最大目的だったので、ちゃんと書かれています。
というか、テレビ版もちゃんと最後まで書かれているので、「説明を言葉で成した」という方がより正確です。
では本題に移ります。
考察というよりは、まとめ、整理です。
アスカの苗字が違う理由
animate
ちゃんと説明してくれてました。
二つ意味があります。
一つは、この映画版とテレビ版を区別する為。
たぶん、こっちが本旨です。
同じキャラクターなのに、苗字が違う。
あくまで別のシナリオとして考えてね! って意義。
本当はこれが目的でしょうが、あくまで作り手の意向なので作品に落とし込みます。
本作に限った話ではなく、他のSFやミステリー作品も大体そうです。定番中の定番。
シン・エヴァンゲリオンでは、新アスカは、テレビ版アスカのクローンだったと、明かされました。
(最後、テレビ版のアスカと合体する)
分かりやすくて良いですね。
パラレルワールドというか、本作はループでしょうか? 最後にカヲル君がそんな話をしていました。
テレビ版の劇場版「まごころを、君に」の後、世界がループしたって事でしょう。
「まごころを、君に」のラストで、アスカは「気持ち悪い」と現実を拒否していましたから。
だから「序」は、初めから(TV版第一話から)やったんですね。
って、これも本当の理由は(エヴァならダイジェストだけで映画にしても売れるという)大人の事情だと思うのですが……、シナリオ上の言い訳に使われてました(笑)
あと、「エヴァンゲリヲン」が「エヴァンゲリオン」になっているのも、ループ、やり直しをしたって表現だと思います。タイトルに反復記号(の終わり)がついてますしね。
正直、こういうのだけで良かった……。
いちいち言葉で説明されると、エヴァっぽくない。
渚カヲル君は、お父さん
animate
別に説明してもらわなくていいのですが、説明されました(笑)
碇ゲンドウは「男」として、ユイを求める人間。
渚カヲルは「父」として、シンジを守りたい人間。
って事らしいです。
だから、最後にゲンドウとシンジは戦います。
父と子の母親をかけた戦いです。
キモイですね。
フランス映画とかにありそうな内容です。
こういうのって、言葉で説明されるとけっこう引きます。テレビ版が秀逸だったのは、この背景構造を語らず、画で濁しているから良かったんです。
ゲンドウはピアノが好きだったとか、別にいらないんですけども……。回想長いし……。
エヴァンゲリオンのシナリオ構造でもっとも重要なテーマが「父と子」であり、シンジ君がメインプロットである以上、ゲンドウはサブプロットなんですね。
サブプロットというのは、主人公の言動(視点)を通して、目的の達成、未達成を視聴者が理解できるのが最もスマートで美しいです。
サブプロット側の人物が語り手になって回想シーンを書くとかは、正直、アマチュア臭くて観ていられませんでした。
まぁ、2.5時間も尺をもらえる人気作で、莫大な数の固定ファンがあるからこそできた事でしょうか。
熱狂的なエヴァファン以外の視聴者にとっては、説教を黙々と説かれているような苦痛がありました。
(某錬金術アニメの映画版を彷彿させる……)
真希波・マリの正体について
animate
新キャラ欲しかっただけだと思います。
こんな何度も何年も固定メンバーでやっていれば、飽きますもの。新メンバー欲しいです。
絶対にこれだと思いますが、そこにも説明が付与されました。
後、なぜか最後にシンジ君の彼女になります。
いる? このオチ。
シナリオ上は必要なのですが、好き勝手やるのがエヴァ(TV版)だったので、劇場版は収まる所に収まった感じです。
「マリ」について。
「マリ」はユイやゲンドウの大学の同級生で、ユイには並々ならぬ思いを持っています。
時系列通りに並べると、
→ ゲンドウがカヲルとして使徒になる
→ 自分も使徒になる(だから歳をとらない)
→ でもユイの想いは、息子が生まれると同時に、そちらへ移行している
→ ユイの母としての想いを受け継ぐ。(継母として意志を受け継ぐ)
→ シンジが父から脱却して独り立ち(本作)
→ マリも肩の荷が下りて再出発(本作)
って感じです。
ネルフに逆らっていたのも、ゲンドウに対立する勢力が必要だからですねー。
こういう物語の中継役を担うキャラクターを、ストーリーテラーと呼びます。
完全にその役割ですね。
で、最後はシンジ君を受け入れます。
「気持ち悪い」なんて言わない。
一緒に旅立ってくれます。
なかなか都合の良い女ですね。
作り手の制御が掛かっているキャラクターで、言動も狙い過ぎていたりしていて、可哀そうなキャラクターに見えました。
只、個人的には、この可哀そうな感じが好きです。
現実と虚構の狭間で色々な役割を持たされる感じが、とても好感で、「シン」では一番良いキャラクターでした。
というか、「シン」のメインは彼女でしたね。登場シーンが多すぎる。
尚、現実と虚構についてはクドクド書かれていて、最後にアニメから絵コンテ、イラストボードに逆行していく場面にも彼女は現れます。
現実と虚構を代弁する役割、の表現でしょうか。
まとめ
二十五年ですかー、長かったですね。
初めの映画版までしかちゃんと観ていませんが、流石に今回で終わりでしょう。
耳にタコができるくらい執拗に「現実に戻る」って述べていたので、アニメは終わり! だと思います。
本作はシリーズ物のラストという点からもファンディスクですので、評価自体は高くありません。(私はファンではなく一般視聴者なので)
庵野さんも「シン」シリーズが好調で新たな居場所がありますし、エヴァの持つお役目も本作で決着が付いたのかな? って思います。
人気作のプレッシャーと戦い続けた姿は、本当に立派でした。
ガイナックス時代よりカラーにかけて、スタッフ皆様、お疲れ様でしたと拍手を送りたいです。
四半世紀、一時代を築く作品と同世代で生きてきた感慨がありますね。
さて、次の世代の覇者は現れるのか?
まだ見ぬ新世紀に、期待しております。